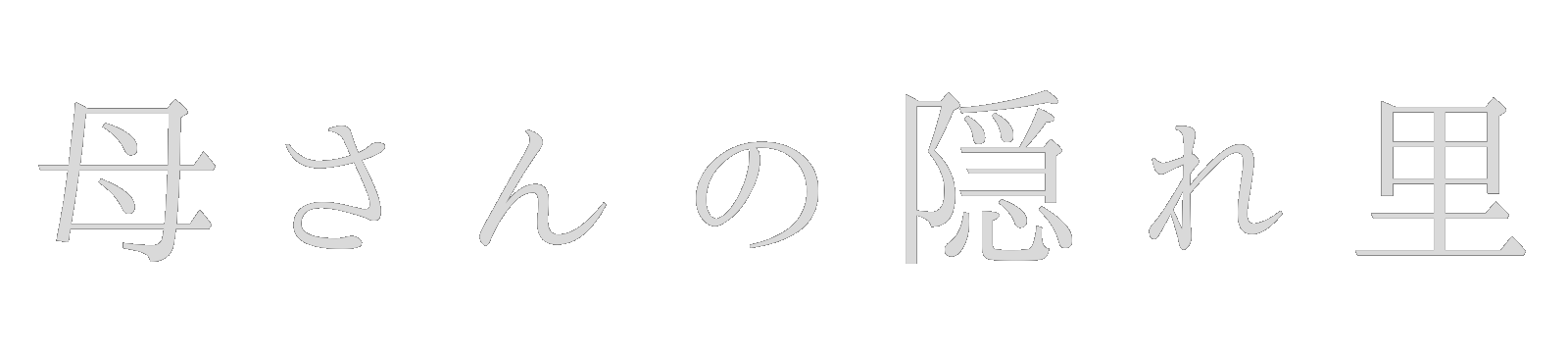お子さんの受験勉強の始まりに、不安を感じているお母さんへ。
「子どもにどのように接したら良いのだろうか」
「なにを準備すべきだろうか」
など、あれこれと悩んでしまうかと思います。
本記事では、これまで3,000名以上の生徒と保護者へ受験指導をしてきた筆者が、大学受験生の親にできることやNG行動、子どもに接する際のポイントなどを解説します。
この記事を読んで、お母さんの不安が少しでも晴れれば幸甚です。
フリーランスWebライター。16年間学習塾の運営・塾長業務に従事したのちライターとして独立。
生徒だけでなく、保護者のお悩み相談・メンタルケアに注力し、子どもの教育環境がより良くなるよう尽力してきました。
「これまでの経験を活かせば、より多くの悩めるお母さんを楽にできるのでは」と思い記事を執筆しています。
大学受験生の親のスタンスはどうして重要なのか?
子どもの受験勉強の成否は、親の接し方にかかっていると言っても過言ではありません。なぜなら、受験はメンタル勝負だからです。
子どもたちのメンタルは大人と比較するとまだまだ不安定ですから、親の一言で絶好調にも絶不調にもなりえます。
「勉強が好きで好きでしょうがない」という子どもはほぼいません。そんな中、「志望校に合格したいから」つらいけど頑張って勉強をしているのです。
だからこそ、親は受験を控えている子どもへの接し方を心得ておく必要があります。
大学受験生の子どもへの接する際のポイント
大学受験生の子どもへ接するとき、最低限押さえてほしいポイントは3つ。
- 常に前向きなコミュニケーションを心がける
- 子どもの選択をできる限り尊重する
- 勉強はプロに任せる
ポイントを押さえることで、子どもは親から「信頼されている」と感じ、安心して勉強に励むことができるようになります。それぞれ詳細を見ていきましょう。
|常に前向きなコミュニケーションを心がける
子どもがどんな状況であれ、親は普段通りの笑顔でいてください。例えば、自分自身が不安を抱えてピリピリしているとき、身近な人がどんな風に接してくれると安心できますか?
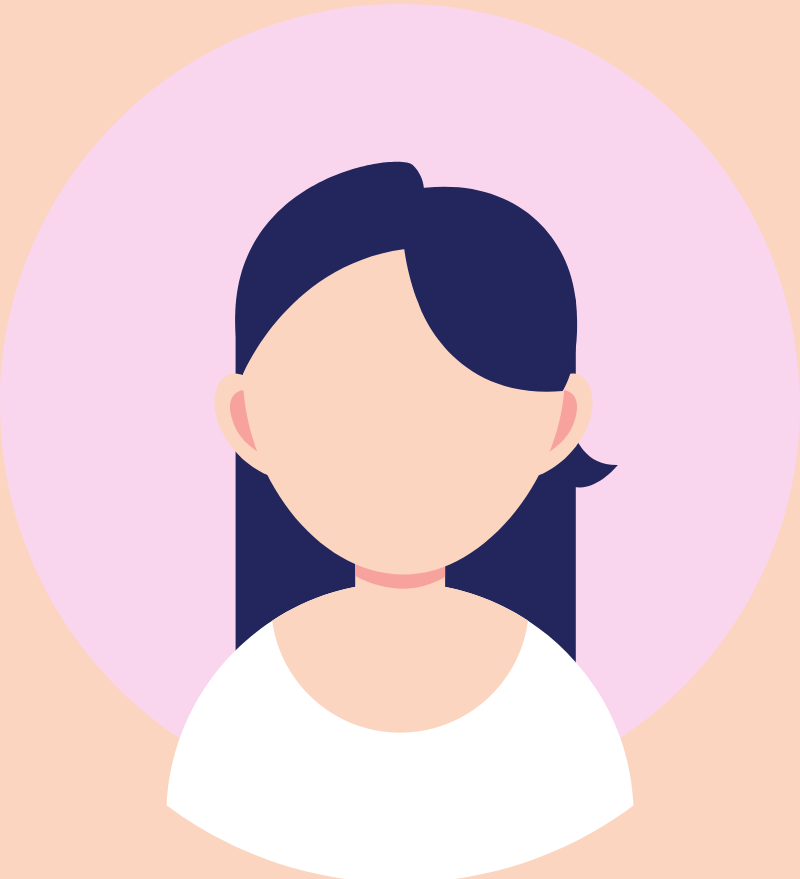
大丈夫だよ
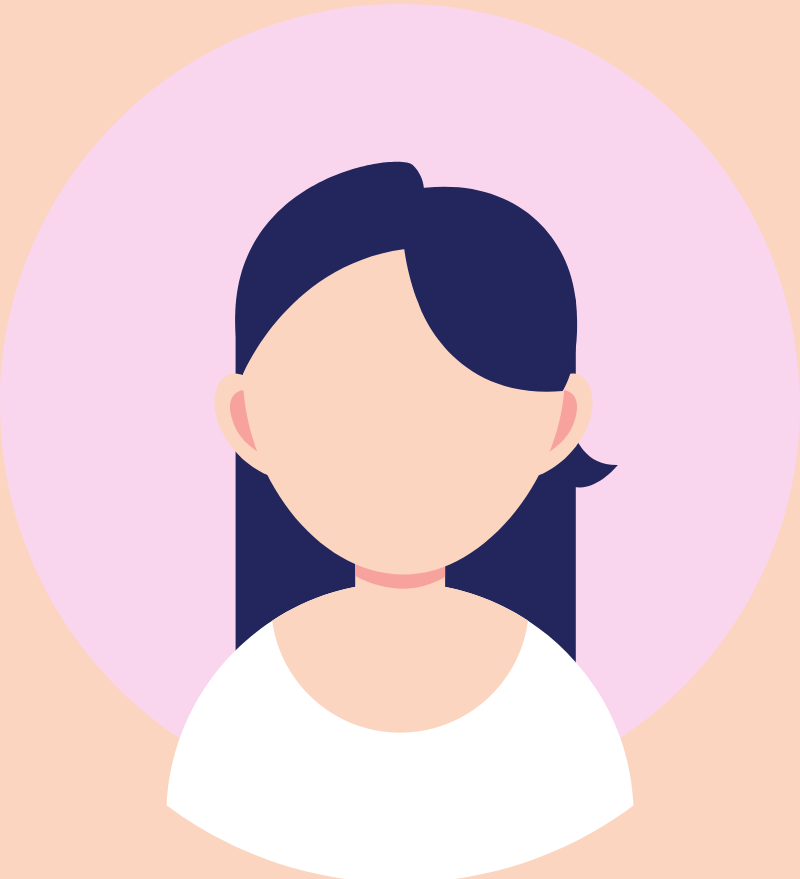
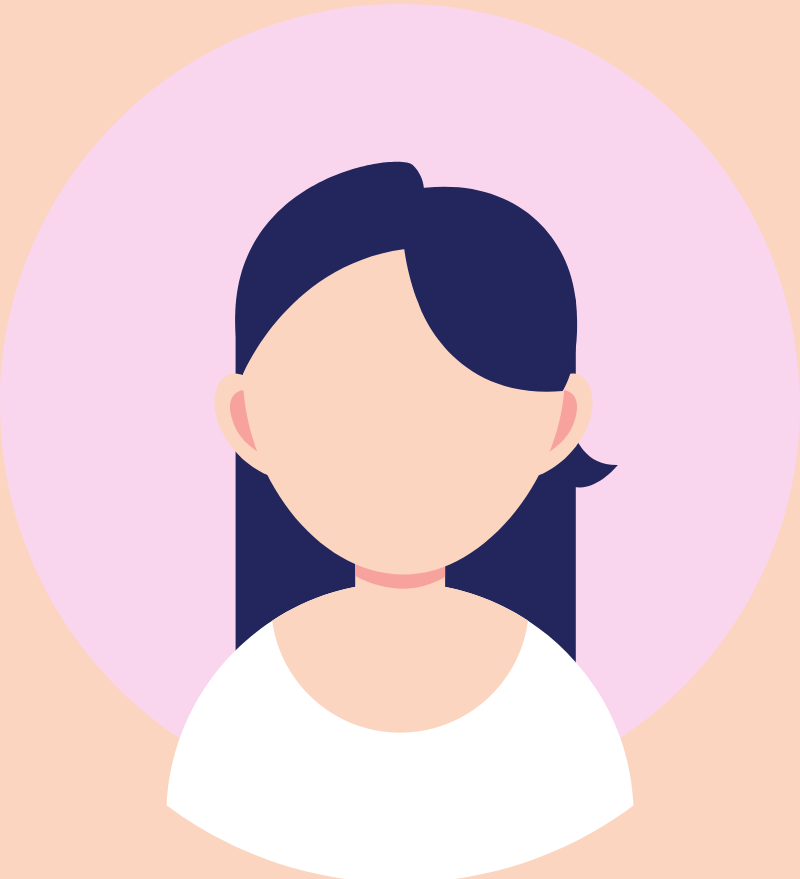
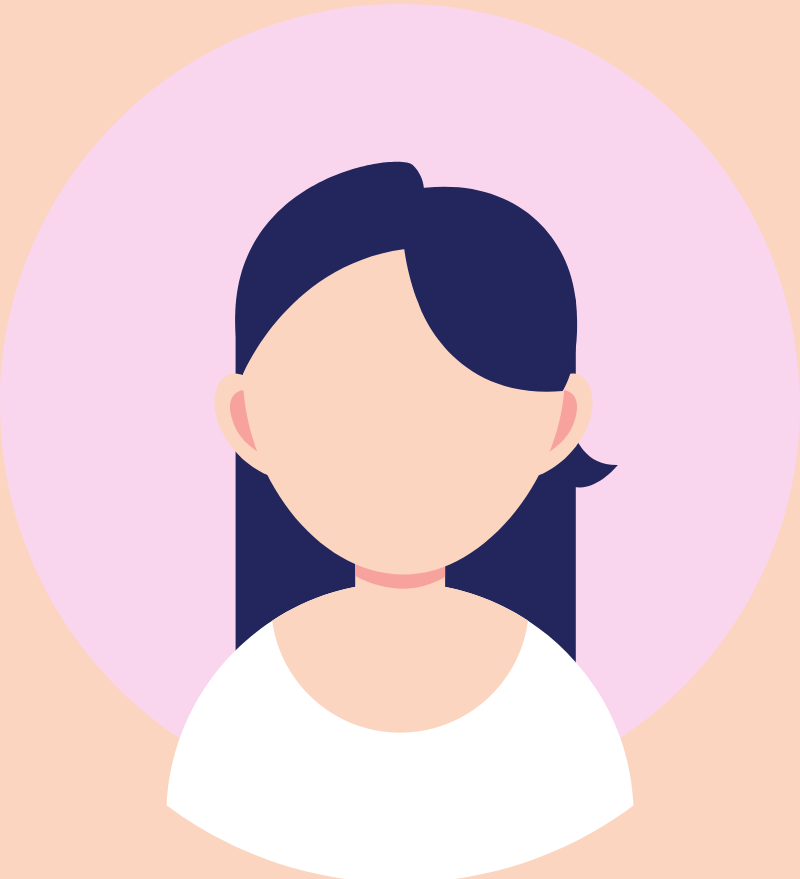
そんなときもあるよ
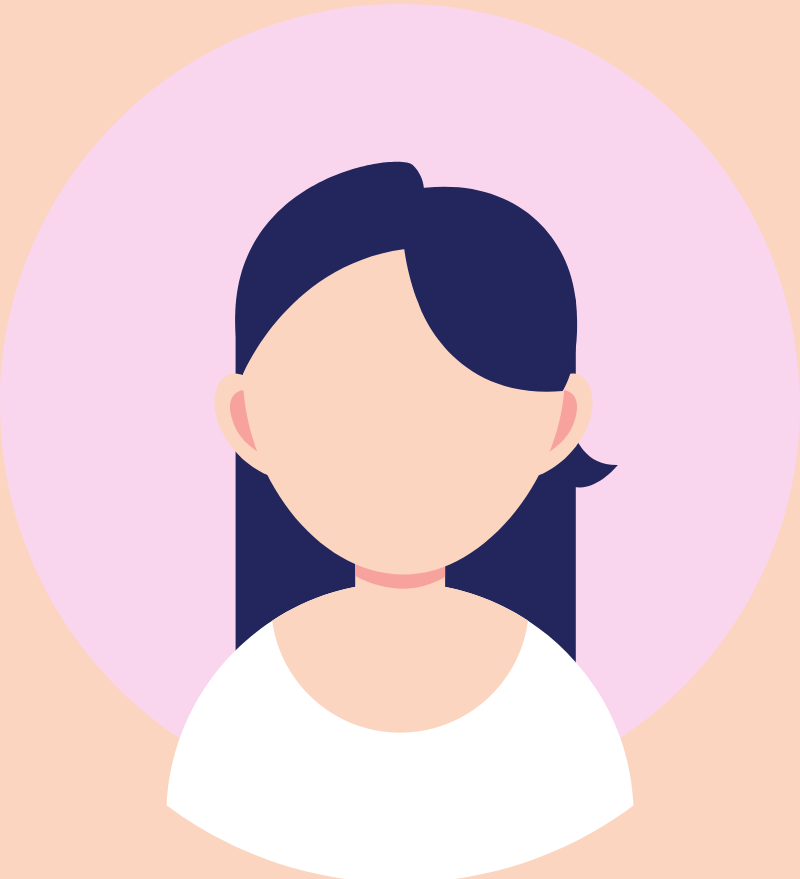
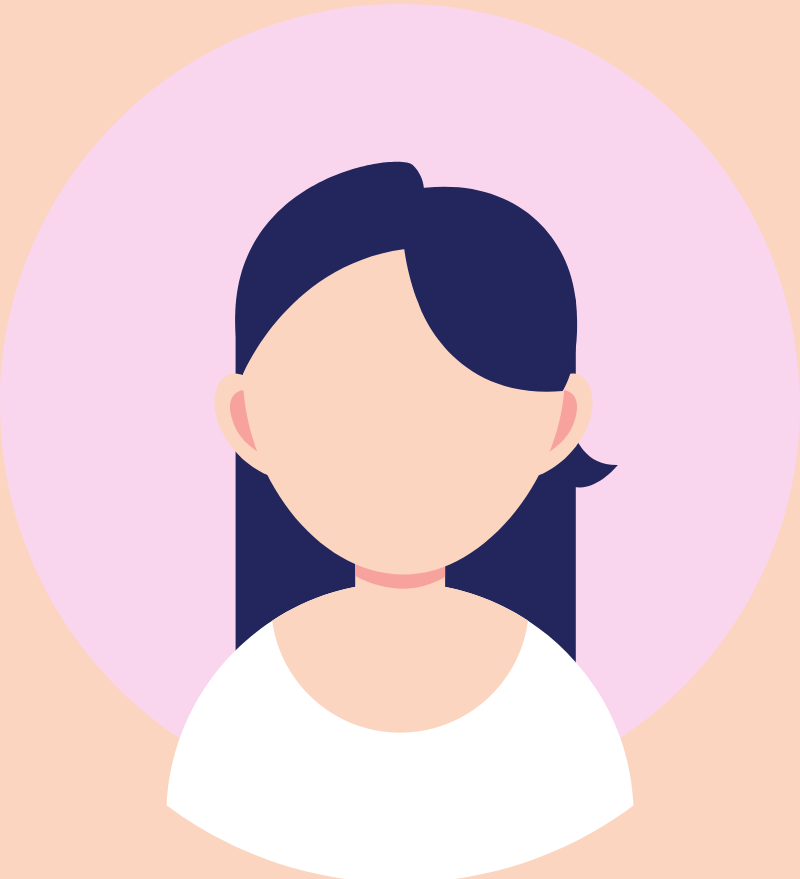
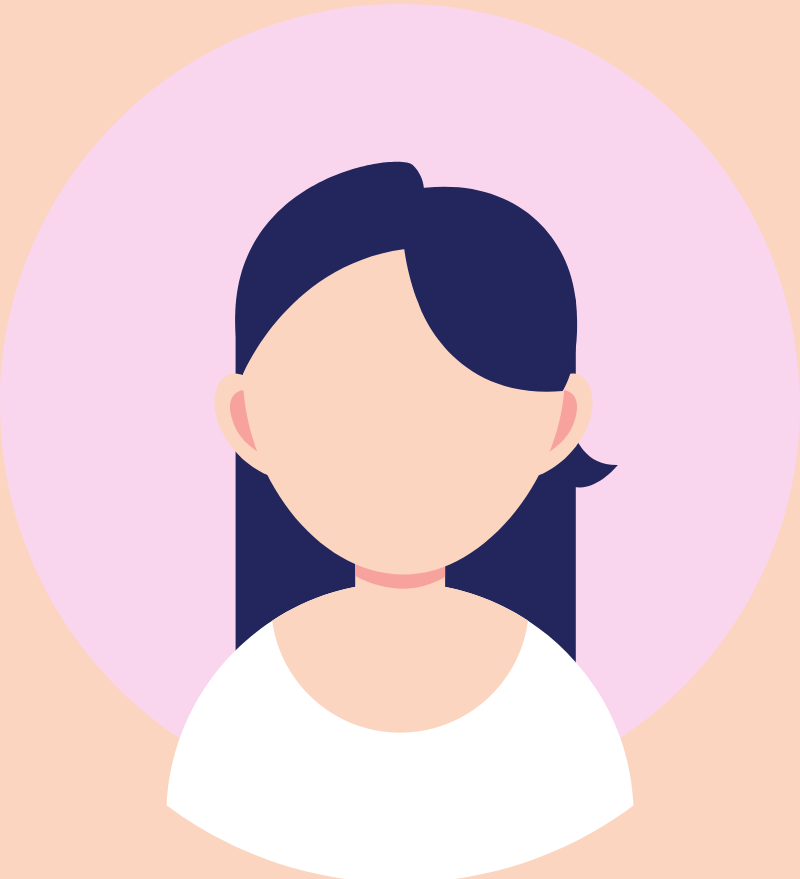
おいしいもの食べて気分転換しよっか
など、前向きさのある言葉が良いですね。
無理にテンションを上げようとしなくて大丈夫です。親が前向きな気持ちでそっと寄り添ってくれていると伝われば、子どもの気持ちも徐々にポジティブになっていきます。
|子どもの選択をできる限り尊重する
子どもを「ひとりの人間」として、尊重する姿勢を持つことが大切です。
子どもに対して
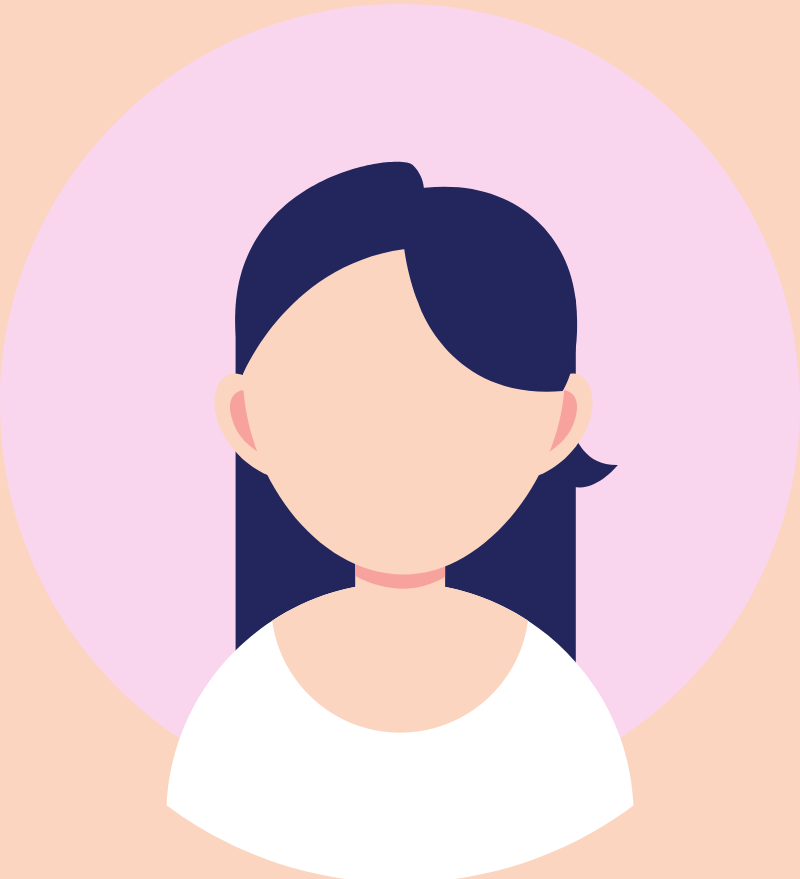
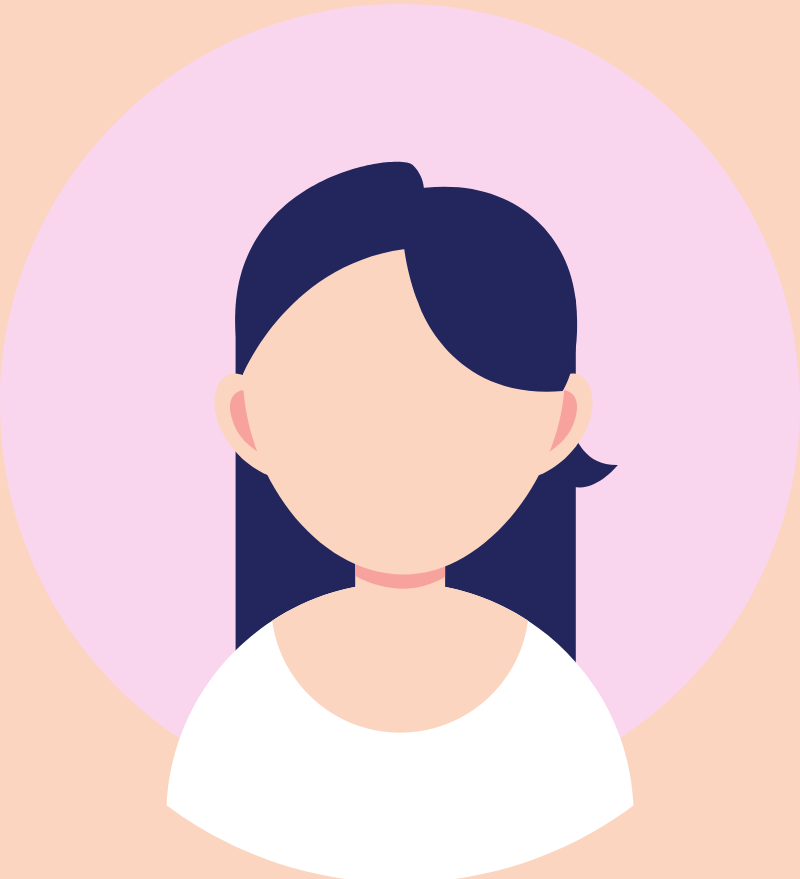
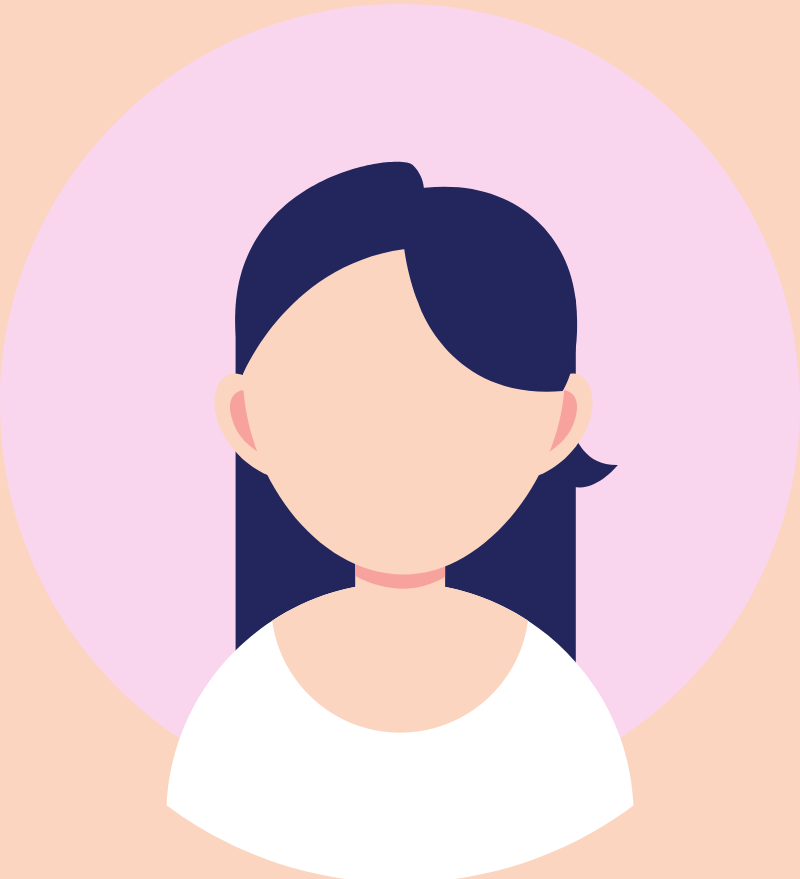
もっとこうすれば良いのに…
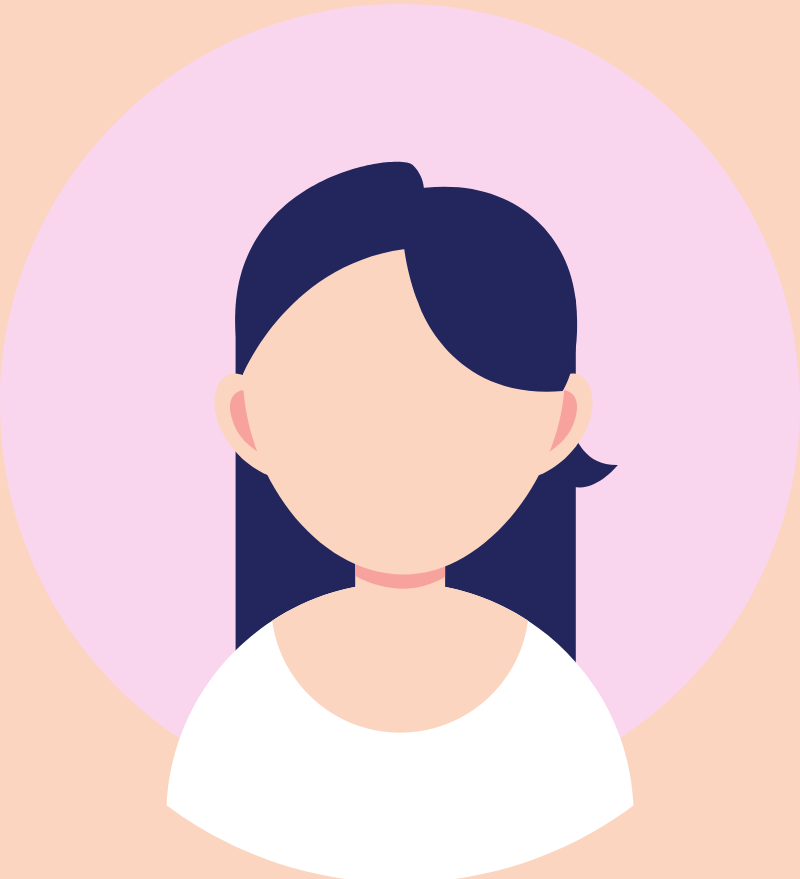
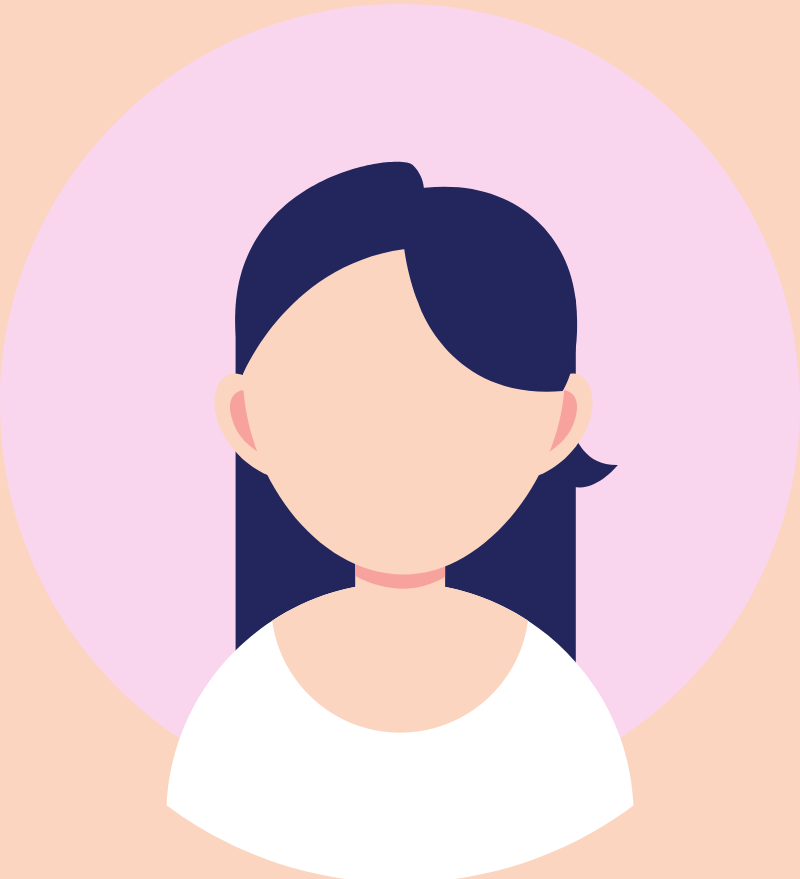
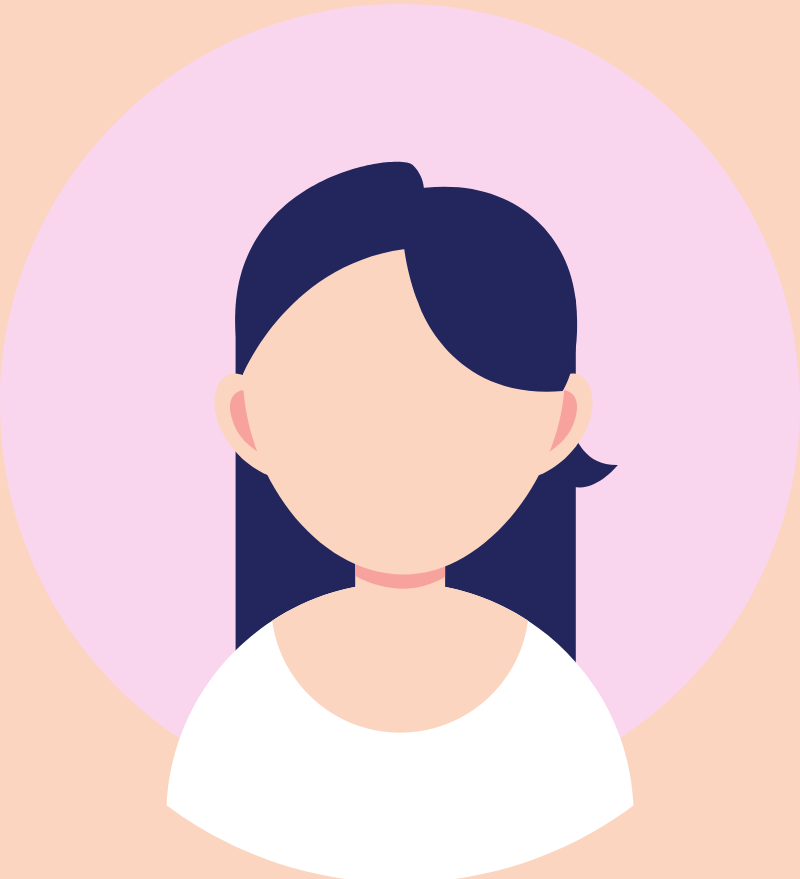
その選択は間違っているんじゃないか…
などとあれこれ気を揉んでしまう気持ちはよく分かります。
しかし、こういった心配が行き過ぎると、子どもは



僕(私)は信頼されていないんだな
と感じます。
子どもの選択や行動に対して、先回りして修正するのは我慢しましょう。
「たとえその選択(行動)が間違っていたとしても、自力で立ち直ることができるだろう」と信じてあげることが、子どもの自己肯定感を育みます。その結果、子どもは自分自身に自信がもて、前向きに勉強できるようになるのです。
志望校・通う塾の選択も、子ども自身にさせましょう。経済的な事情などにより希望を叶えてあげられない場合は、理由をしっかり子どもに説明したうえで、選択肢の修正を一緒に行うことが大切。
あくまで、子どもが「親に決められたのではなく、自分で決めたんだ」と感じられるかどうかがポイントです。
|勉強はプロに任せる
勉強の中身に関しては、思い切ってプロに丸投げしましょう。
子どもたちの学習内容は、数年単位で変化しています。親世代の常識が通用しないのはもちろん、2人目、3人目の子どもが受験生になった際に「上の子のときと同じだろう」と考えるのは危険です。
使用している教科書や問題集も変わっていくため、親が対応していくのはとても大変。
ですから、勉強の中身に関してはヘタに介入せずプロにお任せし、親は子どものメンタルケアと受験制度のリサーチに徹するのが最適な役割分担でしょう。
学校外教育の選び方についてはこちらをご覧ください。
大学受験生の親にできること3選
親が子どもに対してできるサポートは、次の3つを押さえておけば間違いありません。
- 受験の仕組みを理解し、入試までのスケジュールを子どもと共有する
- 子どもの学習環境を整える
- 受験費用を準備する
それぞれ具体的に解説します。
|受験の仕組みを理解し、入試までのスケジュールを子どもと共有する
まずは、大学受験の仕組みを理解することが不可欠です。少々手間がかかりますが、入念に調べることをおすすめします。
子どもは、高校で受験情報を入手できます。しかし高校は、1人ひとりに綿密な受験指導をしきれていないことが多いもの。学校に頼りすぎず、自力で情報をつかみとっていく姿勢が必要不可欠ですので、子どもと一緒にリサーチするのがベストです。
リサーチが不足すると、実力より大幅に低いランクの大学に行くことになってしまったり、不利な受験を強いられたりする可能性があります。これまで16年間学習塾運営に携わる中で、不利な状況に置かれてしまった生徒からのお問い合わせは毎年のようにありました。
わからないことがあったら塾に相談するなど、プロの手を借りることも大切です。
|子どもの学習環境を整える
子どもが勉強に集中できるよう、家族全員で協力する姿勢が大切です。生活音に気を付けたり、快適な室温を保ったりして、「家族全員で受験勉強を応援しているよ」と示してあげましょう。
とはいえ、どんなに家の中の環境を整えたとしても、家では集中して勉強できない子どもがいるのも事実。
「家=休む場所」「学校や塾・カフェなど=勉強する場所」とオンオフをハッキリ分けたい子どもの場合は、家の外に勉強場所を確保してあげることも必要になってきます。
これまで、上記のような子どもを何人も見てきました。「家で勉強できないなんて言い訳だ!」と一蹴する前に、子どもと話し合っておくことをおすすめします。
|受験費用を準備する
子どもを経済的な面で支援するためにも、大学受験にまつわる様々な費用について把握しておきましょう。
以下、必要となる費用の一例です。
| 受験勉強に必要な費用 | 【必須】参考書代 |
|---|---|
| 【必須】模擬試験の受験料 | |
| 資格試験の受験料 | |
| 塾・予備校の授業料 | |
| 試験に関わる費用 | 【必須】入試本番の受験料 |
| 入試日の宿泊費・交通費 | |
| 併願大学への納付金 | |
| 入学決定後に必要な費用 | 入学金・授業料 |
| 一人暮らしをする場合の費用 |
必須の費用以外は、受験校や各ご家庭の費用感によってピンキリです。どこまで費用をかけられるかを見積もり、必要に応じて子どもに伝えておきましょう。
お金に関して、子どもに恩着せがましく言ったり愚痴を聞かせたりするのはNGです。
ただし、自分の家の経済状況を理解することは、大学受験生にとって大切なことでもあります。
本格的な受験期にさしかかる前(高2くらいまで)に一度お話する機会を設けても良いかもしれません。
大学受験生の親がしてはいけないこととNGワード
良かれと思って取った言動が、子どもにとってマイナスにしか働かないことがあります。ここでは受験生の親としてのNG行動・NGワードをまとめておきます。
| 親がしてはいけないこと | NGワードの具体例 |
|---|---|
| 過干渉、口出ししすぎる | ・勉強しなさい ・まだやらないの? ・そのやり方で成績上がるの? |
| 進路を勝手に決めつける | ・○○大学は無理でしょ ・文系はダメ ・医療系に進みなさい |
| お金に関する愚痴を言う | ・これだけお金をかけてるのに… ・誰のお金で受験できると思っているの? |
| 他人と比べた発言をする | ・○○君は偏差値上がったらしいよ ・お姉ちゃんは○○だったのに… |
| 不必要なプレッシャーをかける | ・成績上がらないね ・このままだと間に合わないよ |
| 空気を読まない | ・(成績が落ちたときに)志望校下げたら? ・(休憩時に)そんなことしてる暇あるの? |



時と場合によっては、このような発言が必要なときもありますけどね…
受験期は子どももナーバスになっています。子どもの様子をよく観察し、タイミングをはかって話しかけるようにしてくださいね。
大学受験生の親はストレスを溜めないこと
大学受験生の親として必要なスタンスお伝えしてきました。しかし、ここまで書いたことを全て難なく実践できるお母さんは、ほぼいないでしょう。



なぜなら、所詮きれいごとだからです…
お母さんだって1人の人間。日々さまざまなストレスと戦うなか、仏のように子どもに接するなんて、無理なときももちろんあります。
ですので「あんなこと言わなきゃ良かった…」ということがあっても、自分を責めすぎないでくださいね。
子どものことを第一優先に考えがちですが、お母さんが元気だからこそ、子どもに最善のサポートができることを忘れないでください。
疲れたら、逃げ場を探して癒されましょう。肩の力が抜けているくらいのスタンスが、子どもにとっては一番居心地が良いものです。
まとめ
この記事を読んでくださったお母さんは、今日から前向きな姿勢を忘れずに子どもと向き合ってくださることと思います。
これから整えていくべきサポート体制は以下のとおり。
- 受験の仕組みを理解し、入試までのスケジュールを子どもと共有する
- 子どもの学習環境を整える
- 受験費用を準備する
全て実践するには、お母さんの精神力が欠かせません。不安なとき、疲れているときは、独りで抱え込まずに周りを頼ってくださいね。
この記事が、少しでもお役に立てたなら幸いです。